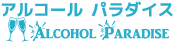9月16日、ベルサール東京日本橋でGI喜多方のスタートアップイベントが開催されました。当日に行われたのが、福島県酒造組合特別顧問の鈴木賢二さんによる基調講演「GI喜多方の解説」です。鈴木さんは、福島県の日本酒を全国トップレベルに引き上げた立役者で、“日本酒の神”とも呼ばれています。
この記事では、基調講演の内容を中心にご紹介します。
目次
全国トップクラスの福島の日本酒
令和5年のデータを見ると、福島県の日本酒生産量は6478キロリットル(全国の約2.1%)となり、生産量は全国10位です。
目立つのは、特定名称酒(原料や製法、精米歩合などの一定の基準を満たした高品質な酒)の比率です。全国平均が43.7%に対して、福島県は75.5%。精米歩合の平均も全国平均61.4%に対して、福島県が57.7%となっています。鈴木さんは、「高級酒志向のお酒が出来上がった」と説明されていました。
質の高さは実績にも現れています。平成18年に金賞の数が日本一になったのを皮切りに、平成22年には再び日本一に。さらに、平成25年以降は、コロナの影響で中止となった令和2年を除いて、9回連続で1位を記録しています。令和7年には、3年ぶりに日本一を奪還しました。
3つのキーワード:芳醇・淡麗・旨口
福島県の日本酒の特徴として挙げられたのは、芳醇・淡麗・旨口です。
芳醇:多種類の吟醸酵母が生み出す香り
淡麗:低温での長期発酵が生む、きめ細かで軽快な味わい
旨口:強い麹からなる、酒本来の旨味や甘み
さらに、口に含んだ後の味わいがスッと消えていく『切れ味』も特徴です。もろみ(酒母・麹・蒸米・水を仕込んで発酵させている状態の液体)のスムーズな管理によって実現されています。
福島県の高品質な日本酒造りを支えているのは、平成4年からスタートした清酒アカデミー事業などの人材育成、盛んな酒蔵同士の情報交換や技術共有、鈴木さんによる片面刷りのA4・2枚にまとめられた吟醸酒製造マニュアルなどによって底上げされた技術力だと説明されていました。
GI喜多方とは
GI喜多方とは、喜多方市の良質な米と水を使用して、喜多方市内で醸されたおいしい純米酒のこと。その特徴を詳しく見ていきましょう。
日本酒造りに適した条件
喜多方市は、福島県の内陸地にある会津地方の最北部にあり、山形県や新潟県に接しています。北西に飯豊連峰の山並みが連なり、東には磐梯山の頂を望む豊かな自然に恵まれている地域です。
夏は気温が高くて稲作に適しており、福島県オリジナルの酒造適合米(酒に適している原料米)である「夢の香」と「福乃香」の栽培が盛んです。
冬は寒冷で、11月から3月はぐっと冷え込み、酒造りに適した気温となります。平均1~2メートルを超す大量の積雪があり、飯豊山に積もった雪が、暖かくなると徐々に溶けて喜多方市の伏流水となり、年間を通して良質な水をもたらします。さらに、水質は日本酒造りに適した軟水です。
低温での醸造は発酵を穏やかにし、吟醸香が高くてきめ細やかな味わいを引き出します。軟水も発酵を穏やかにし、きれいな甘みを生み出します。
こうした条件が、福島の日本酒の特徴である「芳醇・淡麗・旨口」をより強く表現しているのです。
8蔵がGI喜多方に認定
2024年12月20日、以下の8蔵がGI喜多方の認定を受けました。
・峰の雪酒造場
・吉の川酒造店
・会津錦
・笹正宗酒造
・大和川酒造店
・夢心酒造
・ほまれ酒造
・喜多の華酒造場
基調講演後に行われたトークショーでは、今後も品質向上を目指し、認定数を増やしていくつもりだと語られました。
それぞれの蔵が造っているお酒のレポートは、以下の記事で紹介しているのでぜひ合わせてご覧ください。
GI喜多方の蔵元と日本酒が東京に集結!~GI喜多方スタートアップ交流会レポート
知るほどに魅力が深まるGI喜多方
この基調講演では、他にも知ってさらにGI喜多方が楽しめる知識が紹介されました。
例えば、吟醸酵母が生む香りには次の2種類があります。
うつくしま夢酵母など:酢酸イソアミル(バナナやメロン系の香り)
うつくしまきらめき酵母(3種類)など:カプロン酸エチル(リンゴやイチゴ系の香り)
基調講演後に行われた交流会では、こうした香りの違いを実際に体験。さらに、単純な2種類ではなく、味わいの重なりや複雑さも感じられ、GI喜多方の多様性を感じました。
知るほどに魅力が深まるGI喜多方。皆さんもぜひ、それぞれのお酒の個性を自分の舌で味わってみてください。私も今度は現地に行って堪能したいと思っています。