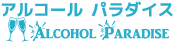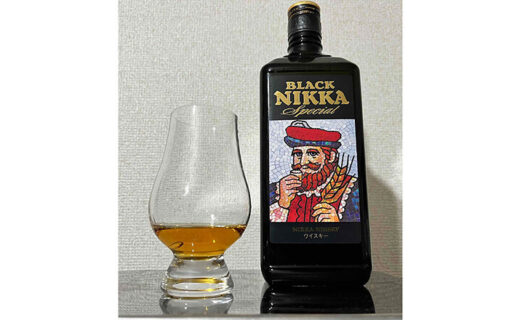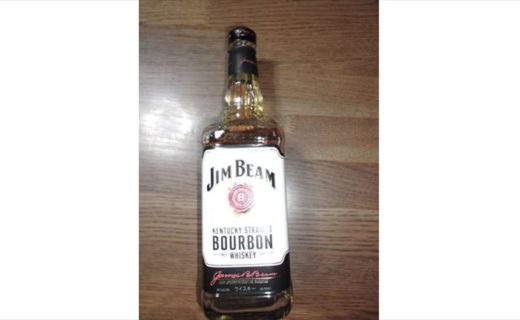福島県二本松市にある1752年創業の大七酒造。日本で唯一、伝統的な「生酛造り」に全面的に取り組んでいる酒蔵として知られています。
その大七酒造では、令和7年7月7日に代表の太田英晴氏が10代目となる太田七右衛門を襲名し、新しい時代を迎えました。
目次
大七酒造とは

大七酒造がこだわり、守り続けている「生酛造り」とは、空中や蔵に棲む乳酸菌を使用して酒母(酛)を造る方法です。現代的な醸造法(速醸法)よりも時間も手間もかかる方法で、自然の力が複雑で奥行きがあり、旨味の豊かな日本酒を生み出します。
大七酒造が酒造り、そして職人を大切にしていることは、厚生労働省が毎年その道の第一人者とされる職人や技術者に贈る称号「現代の名工」が、2人いることからもわかります。ひとりは杜氏である佐藤孝信氏(2016年表彰)、もうひとりは雑味を押さえて酒の透明感と旨味を引き出す「超扁平精米技術」を開発した精米部長の尾形義雄氏(2008年表彰)です。
酒蔵の伝統と精神性を象徴する「太田七右衛門」
今回、太田英晴氏が襲名した「七右衛門」という名は、三代目当主から使われ始めた名前であり、以降の当主が代々受け継いできました。受け継がれているのは名前だけではなく、酒造りの哲学・信念・責任を継承することを意味しています。
https://www.instagram.com/p/DL41EU7zsR_/?hl=ja&img_index=1
太田社長は、福島市で開催された襲名披露会でも「誕生以来名乗ってきた個人名を手放し、歴代の七右衛門という人格の中に加わったことに、身の引き締まるような緊張と責任の重さを感じております」と語っています。
私にとって思い出の日本酒
大七酒造で幅広く親しまれている「大七 生酛」は、私にとって思い出の日本酒でもあります。20年近く前にアメリカ・フロリダ州の小売店で日本酒の販売に携わっていたのですが、当時はまだSAKEが今ほど人気ではなく、RICE WINE(米のワイン)と説明して販売されていました。
試飲販売でも白ワインを思わせるクリーンでフルーティな味わいの日本酒が人気を集める中、「大七 生酛」を好きになってくれれば、きっとまた日本酒を手に取ってくれるはずと思い、しっかり説明できるように勉強し、美味しいと感じてもらえるような楽しい雰囲気づくりに努めていました。私にとって「大七 生酛」は相棒のような存在だったのです。
酒蔵見学もおすすめ

伝統を積み重ね、日本を代表する酒蔵のひとつとなった大七酒造。そのお酒とお酒が造られる現場を、有料で見学できる2種類のツアー(テイスティング付き)があります。いずれも酒造期には仕込み蔵の見学がなく、酒造期かどうかで料金や所要時間が変わります。
●一般見学コース:テイスティング5アイテム
酒造期以外/一人1500円(税込)、所要時間70分程度
酒造期/一人1000円(税込)、所要時間60分程度
●プレミアム見学コース:テイスティング7アイテム
酒造期以外/一人3500円(税込)、所要時間100分程度
酒造期/一人3000円(税込)、所要時間80分程度
*お休み:土曜・日曜・祝日はお休みです(土曜日は、年間で何日か営業)
*申し込みは6名まで
*テイスティングをしなくても料金は同一です
*詳細と申し込みはこちらから→https://www.daishichi.com/information/201910080000
私は2024年3月にプレミアム見学コースに足を運びました。この時期は酒造期の終盤だったため、仕込み蔵の見学はありませんでしたが、江戸時代に殿様から譲り受けたカリンの樹、再利用された以前の建物の梁など、昔からのものを大切にしていることが伝わってくる時間でした。
さらに7種類のプレミアムテイスティングでは、使用するグラスも田崎真也さんのグラスとリーデルの日本酒用のグラスを使用するというプレミアムっぷりです!

当日は運よく現代の名工である杜氏の佐藤孝信氏とすれ違えるという幸運もあり、大七をより好きになれる時間でした。
大七酒造は、都内から3時間もかからずに到着できる酒蔵です。二本松市内には他にも地元の人から愛される檜物屋酒造、木桶造りと瓶貯蔵にこだわる人気酒造、全国的に人気の奥の松酒造など、個性的な酒蔵が並んでいます。
二本松城などの観光地もあるので、今度は1泊2日で、二本松のお酒を満喫したいと思っています。
世界でも愛される大七酒造の世界観にたっぷりと浸れる酒蔵見学。日本酒好きな方は、大七酒造を五感で楽しんでみてください。